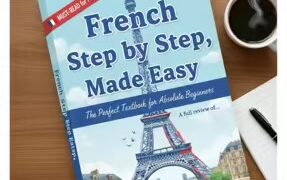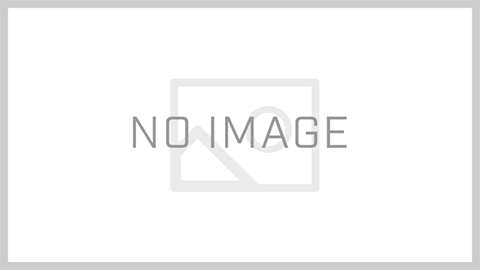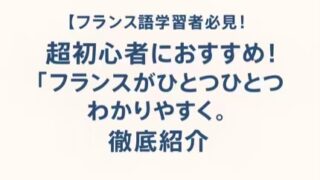今回は、喧騒を離れ、静かに、そして深く神聖な空気に触れる「伊勢の旅」として、伊勢神宮の外宮(げくう)をテーマにご紹介します。
改めて押さえておきたい基本用語や、古来からの習わしである「外宮先祭(げくうせんさい)」の意味も含め、参拝前に知っておきたいエッセンスをまとめました。
皆様が次回参拝するときの参考になれば幸いです。
正式名称は「神宮」
伊勢神宮の正式名称、実は「神宮(じんぐう)」です。内宮は正式には皇大神宮(こうたいじんぐう)、外宮は豊受大神宮(とようけだいじんぐう)と言います。
内宮、外宮にはそれぞれ大小合わせて125社ものお宮があり、それらすべてを含んで神宮と呼びます。
なぜ「外宮」から参拝するのか? ―「外宮先祭」の意味
伊勢神宮へ参拝する際、まず気をつけたいのが順序です。
古来より「外宮先祭(げくうせんさい)」という習わしがあり、外宮を先に参拝し、そのあとに内宮(ないくう)へ向かうのが、正しい参拝の流れとされています。
外宮の御祭神である豊受大御神(とようけのおおみかみ)は、内宮の御祭神(ごさいじん)・天照大御神(あまてらすおおみかみ)の「お食事を司る神」としてお迎えされたので、内宮の祭儀に先だって、外宮で食事を司る神にお食事を奉ります。
この祭典の順序に倣い、参拝もまず外宮から内宮の順にお参りするのがならわしとされているのです。
外宮で意識したい基本用語
知識を頭に入れておくと、参拝中の景色が「ただの森」から「神域」へと変わります。
以下は、特に押さえておきたい用語です。
御正殿(ごしょうでん)
外宮の中心となる最も重要な建物。豊受大御神をお祀りする場所です。
別宮
ご正殿に次ぐ格式を持つお宮で、重要な神様が鎮座されています。外宮には「多賀宮(たかのみや)」「土宮(つちのみや)」「風宮(かぜのみや)」の3つがあります。
唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)
外宮・内宮のご正殿の建築様式。ヒノキの素木(しらき)を用い、切妻造・平入りという特徴を持つ、日本古来の建築様式を今に伝えるものです。
神域(しんいき)/宮域林(きゅういきりん)
神宮の敷地を包む森・林。外宮の境内も豊かな森に包まれており、参道を歩くだけで「神域」へ足を踏み入れたことを実感できます。
これらの知識があると、唯一神明造を見たり、宮域内を歩く際に、深みと感動を得られるでしょう。
参拝スタイル:感謝を捧げる外宮での作法
以下の点を意識して参拝してみましょう。
①参道入口で一礼
鳥居をくぐる前で立ち止まり、軽く一礼するのが基本です。

②手水舎(てみずしゃ)・清め
心身を清め、神域へ入るための準備を整えます。

③ご正殿(正宮)参拝
まずは外宮の中心である豊受大神宮のご正殿へ。別宮を巡る前にこちらを参拝します。

④別宮を巡る
時間に余裕があれば、多賀宮・土宮・風宮も静かに巡ってみましょう。石段を上る多賀宮(高宮)など、少し足を使う場所だからこそ、静かに空気を味わえます。
別宮を参拝する際は、多賀宮→土宮→風宮のルートがおすすめです。
・多賀宮(たかのみや)
ご正宮のすぐ裏手にある、豊受大御神の“荒御魂(あらみたま)”をお祀りするお宮。階段を登った先にあり、力強い気が漂います。個人の願いごとはここで伝えるのがおすすめ。

・土宮(つちのみや)
土地の神様を祀る社。農業や建設関係の仕事をしている人には特にご縁があるといわれます。

・風宮(かぜのみや)
風の神様「級長津彦命」「級長戸辺命」を祀る社。五穀豊穣や災害除けのご利益があるとされます。

これら3つの別宮に回る時間がない、または98段の石段を登るのが難しい場合は、別宮への道に入る前に、別宮遙拝所(べつぐうようはいじょ)という場所から拝むことができます。
(※後日、外宮のもう1つの別宮である月夜見宮についてもお伝えします!)
⑤「感謝」の参拝スタイル
伊勢神宮では「お願いごと」を強くするよりも、「今までの恵みへの感謝」の気持ちを静かに捧げる方がふさわしいとされています。
参拝というと「何かをお願いする」ことに意識が向きがちですが、「まず、今までの恵みに感謝する」という謙虚な姿勢こそ、大人らしい参拝と言えるでしょう。
失礼な行為
・三つ石に手をかざす
最近増えているようですが、注連縄(しめなわ)を貼ってあるにも関わらず、外宮の三つ石に手をかざしたり、お賽銭を入れる人がいます。無礼に当たりますのでやめましょう。

・樹に抱きつく
参道の巨木に抱きついたり、撫でたりする人も後を絶ちません。神域の樹木は神聖なものなので、こちらも触るのはやめましょう。

外宮だからこそ感じられる「森と時間」の魅力
外宮の魅力は、社殿そのものだけではなく、そこを取り囲む森の静けさや、流れる空気感にもあります。

例えば、別宮の一つである多賀宮への石段を上る際。「参拝の途中で一旦息を整える」「立ち止まって木々の間から透ける光を感じる」。
そんな「立ち止まる瞬間」こそ、外宮ならではの静かな時間です。
また、社殿は「唯一神明造」という様式で、簡素ながらに直線的で清楚な美しさがあります。建築・木材・屋根葺き(かやぶき)など、目を凝らすと“日本の原点”とも言える古式ゆかしい構えを目の当たりにします。参拝前にこの建築様式を知っていると、「この屋根のかたち」「この柱の配置」が一段と深く見えてくるはずです。
大人旅のための“深掘り”知識
単なる「観光」ではなく、「信仰・伝統・場としての神宮」を感じるためのヒントとなる、少し深掘りした知識です。
❶私幣禁断(しへいきんだん)
かつては皇室以外からの個人的なお供え物が禁じられていた制度の名残です。現在もご正殿には賽銭箱がなく、白布が敷かれた場所にお賽銭を納める形となっています。
❷式年遷宮(しきねんせんぐう)
20年に一度、社殿・神宝・装束のすべてを新しく造り替え、神様にお遷りいただく壮大なお祭りです。外宮においては、内宮に先んじて行われます。次回は2033年に実施される予定です。
❸ 参道の通行ルール
外宮では左側通行、内宮では右側通行という習わしがあるのをご存知でしょうか。
これは、外宮は手水舎が左に、内宮は右にあるためです。
神域内での立ち居振る舞いを少し意識すると、「自分が参拝者である」感覚が増します。
まとめ
伊勢神宮 外宮」を歩くことは、単に“神社を参拝する”以上の体験です。
それは、千年以上続く祈りの循環を、自分の足でたどる時間でもあります。
・外宮では、お願いよりも「感謝」を。
・知識よりも「静けさ」を。
・そして、形式よりも「心」を大切に。
森に包まれた外宮の境内で、自分の呼吸と神域の空気がゆるやかに重なる瞬間——
そこにこそ、“伊勢詣での原点”があるように思います。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。